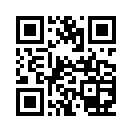2009年10月24日
2. 仕上げと塗装(2回目)
<パテ埋めしている写真>
<研磨している写真>
さてさて、全部の箇所が取り付けられたら、あとは仕上げ。
気を付けてはいたけれど、材木を運んだり付けたりするときにはどうしても擦り傷や凹み、割れなどが生じる。それにどうしても誤魔化せない節の部分などもあるので、木部パテ(※9)で埋めて研磨していく。
<デッキブラシで掃除している写真>
<塗っているときの写真>
デッキブラシで表面の泥やホコリを取り除いて、塗りにくいパーゴラから逃げ場所を確保しながら順次塗っていき一日二日乾燥させたらさあ完成だ!
<塗り終わった後のデッキの写真>
・作り終えて
僕は特に日曜大工でいつもトントン何か作っているわけじゃないから、木工はとてもヘタクソだ。
でも、何かを作るという作業自体は好きだから、頭で妄想してはあんなこといいな、できたらいいなとふらっとホームセンターで電動工具や木材などを眺めてはよく思いにふける。
そんな僕がウッドデッキ という“大物”を実行に移せたのは、いつもそんな妄想をしていたからかもしれない。
木工としては棚とかを作る方が細かいところの荒が見えやすく苦手意識が高いが、ヘタクソな僕でも水平出しと土台部分さえしっかりしておけば、その大物は以外に荒が見えにくく簡単に作れてしまう。
妄想と予算と、あとはホンの少しの度胸のようなものが揃ったとき、後は野となれ山となれ、臨機応変という名の妥協の中ごまかしごまかしなんとか出来ました。
作っている最中から子供は遊び回り友達も連れてきて遊んでくれるなど、庭に遊び場が増えたことによって家が一層賑やかしくなった。
朝起きてまずデッキに出て太陽を拝みながら背伸び、仕事から帰ってきてビール片手にゴロンとする、自然の風と虫の声と青天井。特別に何をするわけじゃない、ただボーっとしていられる空間があることは僕にとって、とても大切なものになりました。
これからどこかに不具合が出てきたりメンテナンスの面もあるけれど、それはそれで楽しんでやっていけたらいいなと思います。
コラム読んで頂きありがとうございました。
※9 木部パテ
木部の補修をするもので、割れや穴など500円玉くらいの大きさ程度ならば目立たずに修正できる。ヘラで圧しこむかのように塗りこみ、200番当たりの紙やすりで削って120番くらいで仕上げると良いでしょう。
水性専用とか油性にも適応しているものとか、あと木材の色別とか色々種類があるので、その木材、塗料に合わせたものを選ぶと良いでしょう。
<研磨している写真>
さてさて、全部の箇所が取り付けられたら、あとは仕上げ。
気を付けてはいたけれど、材木を運んだり付けたりするときにはどうしても擦り傷や凹み、割れなどが生じる。それにどうしても誤魔化せない節の部分などもあるので、木部パテ(※9)で埋めて研磨していく。
<デッキブラシで掃除している写真>
<塗っているときの写真>
デッキブラシで表面の泥やホコリを取り除いて、塗りにくいパーゴラから逃げ場所を確保しながら順次塗っていき一日二日乾燥させたらさあ完成だ!
<塗り終わった後のデッキの写真>
・作り終えて
僕は特に日曜大工でいつもトントン何か作っているわけじゃないから、木工はとてもヘタクソだ。
でも、何かを作るという作業自体は好きだから、頭で妄想してはあんなこといいな、できたらいいなとふらっとホームセンターで電動工具や木材などを眺めてはよく思いにふける。
そんな僕がウッドデッキ という“大物”を実行に移せたのは、いつもそんな妄想をしていたからかもしれない。
木工としては棚とかを作る方が細かいところの荒が見えやすく苦手意識が高いが、ヘタクソな僕でも水平出しと土台部分さえしっかりしておけば、その大物は以外に荒が見えにくく簡単に作れてしまう。
妄想と予算と、あとはホンの少しの度胸のようなものが揃ったとき、後は野となれ山となれ、臨機応変という名の妥協の中ごまかしごまかしなんとか出来ました。
作っている最中から子供は遊び回り友達も連れてきて遊んでくれるなど、庭に遊び場が増えたことによって家が一層賑やかしくなった。
朝起きてまずデッキに出て太陽を拝みながら背伸び、仕事から帰ってきてビール片手にゴロンとする、自然の風と虫の声と青天井。特別に何をするわけじゃない、ただボーっとしていられる空間があることは僕にとって、とても大切なものになりました。
これからどこかに不具合が出てきたりメンテナンスの面もあるけれど、それはそれで楽しんでやっていけたらいいなと思います。
コラム読んで頂きありがとうございました。
※9 木部パテ
木部の補修をするもので、割れや穴など500円玉くらいの大きさ程度ならば目立たずに修正できる。ヘラで圧しこむかのように塗りこみ、200番当たりの紙やすりで削って120番くらいで仕上げると良いでしょう。
水性専用とか油性にも適応しているものとか、あと木材の色別とか色々種類があるので、その木材、塗料に合わせたものを選ぶと良いでしょう。
Posted by ayanpa at 22:34│Comments(0)
│2, 仕上げと塗装(2回目)